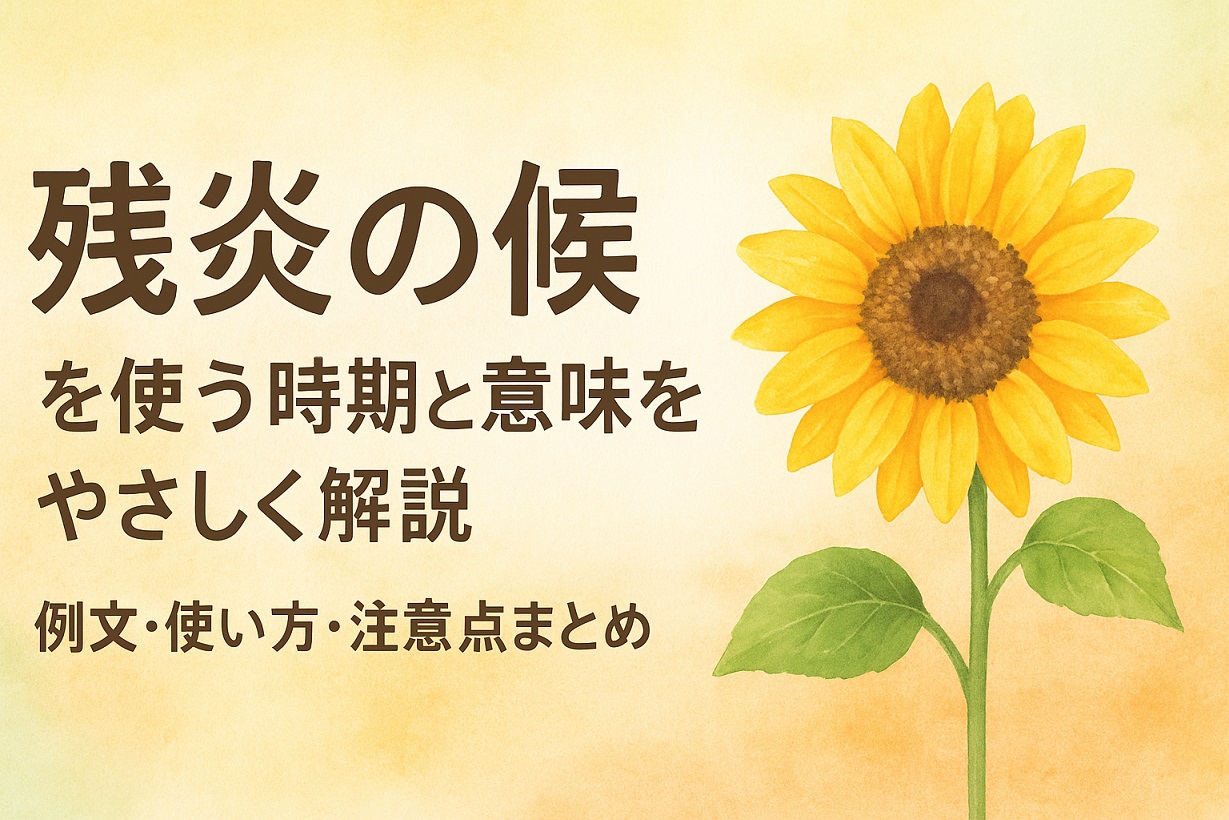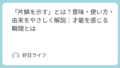目次
- 1 🌻残炎の候を使う時期と意味をやさしく解説|例文・使い方・注意点まとめ
- 1.1 🌸はじめに|「残炎の候」ってどんなときに使うの?
- 1.2 🌞残炎の候を使う時期はいつ?
- 1.3 📖残炎の候の読み方と意味
- 1.4 🌿残炎の候の季節感を感じる風物詩
- 1.5 ✉️残炎の候の使い方とマナー
- 1.6 💬残炎の候と他の挨拶の違い
- 1.7 🪷残炎の候を使うのに適した相手
- 1.8 🚫残炎の候を使わない方がよいケース
- 1.9 💌時候の挨拶としての使い方
- 1.10 ✍️残炎の候を使った例文集
- 1.11 🌼残炎の候の結び文と使い方のコツ
- 1.12 📑コピペOK!残炎の候のテンプレート集
- 1.13 💻Wordで挨拶文を挿入する方法
- 1.14 🌾残炎の候以外の8月の時候の挨拶
- 1.15 🌺まとめ|残炎の候で“夏の余韻”を上品に伝えよう
🌻残炎の候を使う時期と意味をやさしく解説|例文・使い方・注意点まとめ
🌸はじめに|「残炎の候」ってどんなときに使うの?
ビジネスメールや手紙で見かける「残炎の候(ざんえんのこう)」。
聞いたことはあるけれど、「いつ使えばいいの?」「どんな意味?」と迷う方も多いですよね。
この記事では、使う時期・意味・読み方・文例・注意点までを、初心者の方にもわかりやすく解説します。
🌞残炎の候を使う時期はいつ?
残炎の候はいつからいつまで?
「残炎の候」は、8月中旬から下旬に使われる時候の挨拶です。
この頃は、太陽の光がやや柔らかくなり、日差しの中にも少しずつ秋の気配が混じり始める時期。
昼間はまだ汗ばむような暑さですが、朝晩は涼しさを感じるようになり、虫の声や空の色にも季節の移ろいが現れます。
地域によって気候差はありますが、おおよそお盆を過ぎてから8月末までを目安に使うとよいでしょう。
この時期は、夏の疲れが出やすい頃でもあるため、体調を気づかう一言を添えると、よりやさしく温かい印象を与えられます。
なぜ8月1日〜6日は使えないのか?
8月7日ごろは立秋と呼ばれ、暦の上では秋の始まりです。
そのため、それ以前(8月1日〜6日)はまだ真夏にあたるため、「残炎の候」はやや早すぎる印象になります。
代わりに「盛夏の候」や「炎暑の候」を使うのが自然です。
また、地域によっては立秋前でも暑さが続くことがありますが、文面では暦を基準にするのがマナーです。
「季節を先取りする」気持ちで立秋以降に使うと、より上品な印象になります。
「残炎の候」がふさわしい季節感
イメージとしては、日中は汗ばむような暑さでも、夕暮れにふと涼しい風を感じる頃。
日が傾くのが少し早くなり、セミの声も静まり、夜には鈴虫の音が聞こえ始めるような時期です。
そんな“夏の終わりの余韻”を伝える言葉が「残炎の候」です。
手紙やメールに添えると、相手に季節の情緒を感じてもらえ、丁寧で品のある印象を残すことができます。
📖残炎の候の読み方と意味
読み方
「ざんえんのこう」と読みます。
「残炎(ざんえん)」の「炎」は、火のように強く照りつける夏の太陽の象徴であり、
「候(こう)」は“季節”や“時期”を表す言葉です。
そのため、この表現には「夏の炎の名残が感じられる頃」という意味が込められています。
意味と由来
「残る炎」という言葉には、ただ物理的な暑さだけでなく、
夏のエネルギーや命の輝きがゆっくりと静まっていく様子が重ねられています。
日本語の季語としても美しく、古くから手紙や俳句の世界で使われてきました。
「残炎の候」は、暑さの中にも季節の移ろいを感じる繊細な表現であり、
夏を惜しむ気持ちや、次の季節への期待をやさしく伝える言葉でもあります。
また、「炎暑」ほど激しい暑さではなく、「残暑」よりも少し早い時期に使うのが特徴です。
「炎暑」「残暑」との違い
| 表現 | 時期 | 意味のニュアンス |
|---|---|---|
| 炎暑の候 | 7月下旬 | 一年で最も暑く、力強い太陽を感じる時期 |
| 残炎の候 | 8月中旬 | 暑さがやや和らぎ、夏の名残を感じる穏やかな時期 |
| 残暑の候 | 8月下旬〜9月初旬 | 暦の上で秋になった後も残る暑さを指す |
| このように、「残炎の候」は“夏の終わりを惜しみながらも、まだ少し熱気を感じる時期”を | ||
| 情緒的に表した中間的な挨拶言葉として使われています。 |
🌿残炎の候の季節感を感じる風物詩
夏の終わりを感じる自然の変化
夕方の空がやわらかく染まり、虫の声が響き始める頃。
セミの声も遠くなり、少しずつ秋の足音が近づいてきます。
日中はまだ眩しいほどの陽射しが降り注ぎますが、夕暮れになると西の空がオレンジから紫へとゆっくりと変化し、どこか物寂しい雰囲気が漂います。
木々の葉の色がわずかに変わり始め、庭先の草花も夏の疲れを感じさせるようにうなだれています。
そんな小さな自然の変化が、季節の移ろいを教えてくれる時期です。
風が肌に当たる感覚もやわらぎ、夜には鈴虫やコオロギの声が交じり、心地よい静けさが広がります。
食べ物・行事に見る“残炎のころ”
冷たいそうめんやスイカ、アイスがまだ恋しい季節。
しかし一方で、炊き込みご飯や冷ややっこなど、少し温かみのある料理を恋しく感じる人も増えてきます。
お盆や花火大会、灯籠流しといった夏の行事が次々と終わりを迎え、家族や友人との再会の余韻を味わう頃です。
この時期の夜風は少し湿り気を帯びながらも、どこか秋を運んでくるような優しさを感じさせます。
手紙に添える季節の話題例
「夏の終わりに、少しずつ風が涼しくなってまいりましたね。」
「蝉の声もやわらぎ、秋の気配を感じる今日この頃です。」などの一文を添えると、柔らかな印象になります。
ほかにも、「夕暮れの空に秋の雲が浮かび、過ぎゆく季節を感じます。」や「花火の音も遠のき、夜風が少し冷たくなりましたね。」など、情景を交えた一文を添えると、より詩的であたたかな雰囲気を伝えられます。
✉️残炎の候の使い方とマナー
旧暦と新暦の違いに注意
旧暦では7月下旬、新暦では8月中旬〜下旬にあたります。
旧暦(太陰太陽暦)は月の満ち欠けを基準にしていたため、今の暦と季節のずれが約1か月ほどあります。
そのため、昔の人々が感じていた「残炎の候」は、現在の暦でいえばお盆を過ぎた頃、夏がゆっくりと終わりを迎える時期に重なります。
暦の違いを意識しながら、現代の気候や地域の季節感に合わせて使うことが大切です。
特に、北海道や東北など涼しくなるのが早い地域ではやや早めに使うと自然に感じられ、関西・九州などでは8月末ごろまで使っても違和感がありません。
このように、旧暦と新暦の差を理解しておくと、相手に違和感のない丁寧な表現ができます。
使う理由と季節感の表現
「残炎の候」は、まだ暑さが残る中にも、季節の移ろいを感じさせる言葉です。
「夏の名残を楽しむ」ような優しいニュアンスがあります。
同時に、この言葉には“暑さを我慢する大変さ”だけでなく、“次の季節を待ち望む穏やかな気持ち”が込められています。
日本では、季節の変化に寄り添う表現が古くから大切にされており、「残炎の候」もそのひとつ。
暑さの中にも秋の気配を感じ取ることで、相手に「季節を一緒に感じる心」を伝えることができます。
ビジネス・プライベートでの使い分け
ビジネスでは丁寧で上品な印象を与えます。
特に取引先や上司に使う場合は、「残炎の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。」など、フォーマルな表現が適しています。
親しい人への手紙では、もう少し柔らかく「暑さも少し落ち着いてきましたね」「夏の終わりを感じますね」などでもOKです。
また、親しい友人同士なら、「夜風が気持ちよくなってきましたね」など、季節を感じさせる一言を添えると、やさしく温かな印象になります。
💬残炎の候と他の挨拶の違い
「残炎の候」と「残暑の候」「晩夏の候」の違い
「残炎の候」「残暑の候」「晩夏の候」はいずれも、夏の終わりを表す挨拶ですが、それぞれのニュアンスや使う時期には微妙な違いがあります。
たとえば、「残炎の候」はまだ強い日差しが感じられる8月中旬に使う、ややフォーマルで格式のある表現です。
「残暑の候」は立秋を過ぎてからの8月中旬〜下旬、暦の上では秋に入りながらも暑さが残る時期に用いられます。ビジネス文書だけでなく、友人や家族への手紙にも使いやすい、もっとも一般的な季節の挨拶です。
一方、「晩夏の候」は8月下旬から9月初旬にかけて、暑さが落ち着き、秋の気配がはっきり感じられる頃に使います。言葉の響きに落ち着きと上品さがあり、手紙に季節の余韻を残したいときにぴったりです。
また、使う相手や文章のトーンによっても選び方が変わります。
フォーマルな場では「残炎の候」、親しみを込めたいときは「残暑の候」、静かな季節の移ろいを表現したい場合には「晩夏の候」といったように使い分けると、より洗練された印象になります。
🪷残炎の候を使うのに適した相手
ビジネス文書(取引先・顧客)
フォーマルな印象を与えたいときにぴったりです。
「残炎の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。」のように使うと丁寧です。
また、長年のお付き合いのある取引先などには、時候の挨拶に加えて「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」などの感謝の一文を入れると、より心のこもった印象になります。
さらに、季節の話題を軽く添えると、堅苦しさが和らぎ、読み手に親しみを感じてもらえます。たとえば「厳しい暑さの中にも、夕暮れに秋の気配が感じられるようになりました。」などがおすすめです。
目上の人(先生・上司など)
「残炎の候、先生におかれましてはますますご健勝のことと拝察申し上げます。」など、敬語を添えるとより丁寧になります。
相手が上司や恩師などの場合は、文面全体を少し長めにして「平素よりご指導を賜り、心より感謝申し上げます。」といった感謝の気持ちを加えると、誠実で品のある印象になります。
また、堅い文体の中にもやさしさを添えるために、「季節の変わり目ですので、くれぐれもご自愛くださいませ。」のような一文を結びに加えるとバランスが取れます。
親しい人に使う場合
「残炎の候」は少し堅く感じられるため、「まだ暑い日が続きますね」「夏の終わりを感じますね」といった柔らかい言葉に言い換えても大丈夫です。
親しい友人や家族宛の手紙では、「夜風が心地よくなってきましたね」や「夏の疲れが出やすい頃ですが、元気に過ごしていますか?」など、相手の体調を気づかう言葉を添えると温かみが増します。
SNSやメッセージアプリなどで使う場合は、「夏もあと少しですね」など、軽やかな表現に変えてもよいでしょう。
🚫残炎の候を使わない方がよいケース
「残炎の候」はとても上品で季節感のある表現ですが、使うタイミングを誤ると相手に違和感を与えることがあります。
特に以下のようなケースでは避けたほうが無難です。
- 8月上旬(立秋前)には使わない
暦の上で夏真っ盛りの時期に使うと、季節のずれを感じさせてしまいます。
この時期には「盛夏の候」「炎暑の候」など、より真夏にふさわしい挨拶を選びましょう。
また、地域によっては立秋が過ぎても暑さが続くことがありますが、手紙では暦に合わせるのが基本です。
「季節を少し先取りする」くらいの意識で使うと上品な印象になります。 - SNSやカジュアルなメッセージでは不自然
「残炎の候」はビジネスや改まった手紙に使う表現なので、友人とのLINEやSNS投稿などではやや堅苦しく感じられます。
その場合は「まだ暑いですね」「夏もそろそろ終わりですね」などの自然な言葉の方が親しみやすく伝わります。
季節感を出したい場合は、絵文字や写真などで表現するのも良いでしょう。 - 9月以降は「残暑の候」や「初秋の候」に切り替える
9月になると暦の上ではすでに秋に入り、「残炎の候」は季節外れの表現になってしまいます。
9月上旬は「残暑の候」、9月中旬以降は「初秋の候」や「秋涼の候」などを使うと自然です。
また、残炎の候はあくまで「夏の余韻」を伝えるための表現であることを意識して、使い時を逃さないようにしましょう。
💌時候の挨拶としての使い方
基本構成
- 頭語(拝啓など)
→ 手紙やメールの最初に添える丁寧な呼びかけの言葉です。「拝啓」「謹啓」など、相手との関係性や文面のフォーマルさに応じて使い分けましょう。 - 時候の挨拶(残炎の候〜)
→ 季節を感じさせる一文で、文章全体の雰囲気をやわらげます。「残炎の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。」など、相手への敬意と季節感を同時に伝えます。 - 相手の安否をたずねる文
→ 「いかがお過ごしでしょうか」「お元気でお過ごしのことと存じます」など、相手の健康や近況を気づかう言葉を添えることで、あたたかみのある文章になります。 - 本文
→ 用件や伝えたい内容を簡潔かつ丁寧に述べる部分です。季節の挨拶から自然に流れるように本題へ入ると、美しくまとまります。 - 結びの挨拶(ご自愛ください など)
→ 季節に合わせて相手の健康を気づかう言葉を入れるのがポイントです。「暑さ厳しき折、くれぐれもお体をお大事に。」などが一般的です。文末に「敬具」「草々」などの結語を添えると、より丁寧な印象になります。
例文
拝啓 残炎の候、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
まだ日中は暑さが残りますが、お体にお気をつけてお過ごしください。
夕暮れ時には少しずつ涼しい風が感じられるようになりましたね。
季節の変わり目、どうぞお体を大切にお過ごしくださいませ。
✍️残炎の候を使った例文集
ビジネスで使う場合
拝啓 残炎の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
猛暑の折、皆様のご健康をお祈り申し上げます。
立秋を過ぎても厳しい暑さが続いておりますが、貴社におかれましては業務ご順調のことと拝察いたします。
今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
季節の変わり目ですので、どうぞご自愛くださいませ。
このように、ビジネスの文面では時候の挨拶に加えて、相手企業の発展を願う一文や今後の関係性を示す表現を加えると、より誠実で印象の良い文章になります。
目上の人に使う場合
拝啓 残炎の候、先生におかれましてはますますご清祥のことと存じます。
くれぐれもお体を大切にお過ごしくださいませ。
まだ日中は汗ばむ日が続いておりますが、夕暮れには秋の気配が感じられるようになりました。
日々ご多忙のことと存じますが、健康には十分ご留意ください。
今後ともご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
このように、敬意を表しながらも季節感を織り交ぜた文にすることで、上品で温かみのある印象になります。
親しい人に使う場合
残炎の候、少しずつ夜風が心地よくなってきましたね。
お盆も過ぎ、夏の終わりを感じる今日この頃です。お元気ですか?
今年の夏もいろいろな思い出ができましたね。
夕暮れ時の涼しさに少しほっとする反面、夏の終わりに少し寂しさを覚えます。
近いうちにまたお会いできるのを楽しみにしています。
親しい人への手紙では、相手との関係性を大切にしながら、思い出や共感を交えることで、よりあたたかく自然な印象を与えることができます。
🌼残炎の候の結び文と使い方のコツ
結び文の例
- 残暑厳しき折、どうぞご自愛くださいませ。
→ ビジネスでもプライベートでも使いやすい定番の表現です。夏の疲れが出やすい時期に、相手の健康を気づかうやさしさが伝わります。 - 季節の変わり目ですので、お体を大切にお過ごしください。
→ 季節の変化を意識させる穏やかな一文で、幅広い相手に使えます。特に目上の人や取引先への結びとしても好印象です。 - これからもお健やかにお過ごしになられますようお祈り申し上げます。
→ 丁寧で上品な印象を与える表現で、改まった手紙やフォーマルな挨拶文にも最適です。 - 夜風が心地よくなってまいりましたが、どうぞお体を冷やされませんように。
→ 季節の情景を交えたやさしい表現で、親しい人やお世話になった方へのお便りに向いています。 - 夏の終わりに向け、実り多い日々をお過ごしくださいませ。
→ 相手の幸せや今後の健やかな日々を願う、前向きであたたかい印象を与えます。
コツ
冒頭の時候の挨拶と季節感を合わせることで、文章全体に統一感が出ます。
また、結び文のトーンを相手との関係性に合わせて調整すると、より自然で心に残る締めくくりになります。
ビジネスでは「ご自愛くださいませ」のような定型的で丁寧な言葉を、友人宛では「体調を崩さないようにね」といった柔らかい言い回しを選ぶと良いでしょう。
相手の立場や距離感を意識して選ぶことで、あなたの文章により深みと優しさが生まれます。
📑コピペOK!残炎の候のテンプレート集
ビジネスメール例
残炎の候、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
猛暑の折、どうぞご自愛くださいませ。
立秋を迎え、日中の暑さの中にも少しずつ秋の気配を感じるようになりました。
今後とも変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
このように、ビジネスメールでは感謝と季節の挨拶を両立させることで、丁寧かつ温かい印象を与えられます。
「残炎の候」はフォーマルな文面に自然に溶け込みやすい言葉なので、営業メールや季節のご挨拶文としても重宝します。
暑中見舞い・残暑見舞い文例
残炎の候、まだまだ暑い日が続きますが、どうぞお体を大切に。
涼しい秋が待ち遠しいですね。
今年の夏もたくさんの思い出ができましたでしょうか?
少しずつ日が短くなり、夕方の風が心地よく感じられるようになりました。
どうぞ季節の変わり目に体調を崩されませんようご自愛くださいませ。
このような文例は、葉書やメールの季節の挨拶にぴったりで、絵柄入りのカードに添えるとより印象的です。
親しい人への手紙文例
残炎の候、夏の終わりを感じる夕暮れ時にふとあなたを思い出しました。
お元気に過ごしていますか?
夕暮れの空が少しずつ秋色に染まり、セミの声が遠のいていくのを聞くと、どこか切なさを感じますね。
この時期は夏の疲れが出やすい頃ですので、無理をせずゆっくりお過ごしください。
次に会える日を楽しみにしています。
こうした一文を加えることで、手紙全体にやさしさとぬくもりが増し、相手の心にそっと寄り添うような文章になります。
💻Wordで挨拶文を挿入する方法
手順
- Wordを開く
→ 文書を新規作成したら、まずフォントや余白などを整えておくと仕上がりがきれいになります。 - メニューから「挿入」→「あいさつ文」→「季節の挨拶」を選択
→ Wordの機能を使うと、時候の挨拶や結びの言葉を自動で挿入できるため、とても便利です。 - 表示された候補から「残炎の候」を選ぶだけ!
→ 挨拶文は一覧形式で表示され、季節ごとの言葉が簡単に選べます。
「残炎の候」を選択すると、すぐに文書内に反映され、ビジネスメールや手紙の冒頭が整います。 - 必要に応じて文面をアレンジ
→ 相手や状況に合わせて「ご清祥のこととお喜び申し上げます」などを加えると、より丁寧な印象になります。
ポイント
- 日付設定を変えると、自動でその季節に合ったおすすめの挨拶文が表示されます。
たとえば8月中旬に設定すれば、「残炎の候」「残暑の候」などが候補に出てきます。 - ビジネス文書を作るときに非常に便利で、取引先への手紙やお礼状、案内状などにもすぐ活用できます。
- Wordのテンプレート機能と組み合わせれば、会社ロゴ入りの文書や個人用の定型文を簡単に作成できるのも魅力です。
- 挨拶文の自動挿入を使うことで、手紙作成がぐっとスムーズになり、文面の印象も統一感が出ます。
🌾残炎の候以外の8月の時候の挨拶
8月は季節の変わり目であり、使える時候の挨拶がとても多彩です。
それぞれの挨拶には独自の意味と時期があり、使い分けることで文章に深みが生まれます。以下に代表的なものを詳しく紹介します。
- 大暑の候(7月下旬)
一年で最も暑さが厳しい時期に使われます。太陽が真上にあり、夏のピークを象徴する表現です。
「酷暑の折、どうぞご自愛くださいませ。」などの一文を添えると自然です。 - 立秋の候(8月7日ごろ)
暦の上では秋の始まりを告げる時期。とはいえ、まだ残る暑さを感じながらも、空や風に秋の気配を見つけられる頃です。
「朝夕の風に少しずつ秋を感じますね。」などの一文を加えると上品です。 - 残暑の候(8月中旬〜下旬)
立秋を過ぎてもなお暑さが続く時期に使われます。もっともポピュラーな夏の終わりの挨拶で、ビジネス・プライベートどちらにも使いやすい言葉です。
「暑さの中にも秋の訪れを感じるようになりましたね。」などが好印象です。 - 初秋の候(8月下旬)
秋の訪れを感じ始める穏やかな時期を指します。暑さが落ち着き、空気が少し澄んでくる頃です。
「朝晩の涼しさに秋の気配を感じるようになりました。」などの言葉と組み合わせると、やさしい雰囲気が伝わります。 - 処暑の候(8月23日ごろ〜)
「暑さがようやくおさまる」という意味を持つ二十四節気のひとつ。
夏の終わりと秋の入り口を感じる表現で、落ち着いた印象を与えます。
「日中はまだ暑さが残りますが、夜は過ごしやすくなりましたね。」などと続けると、自然で美しい季節感を表せます。
🌺まとめ|残炎の候で“夏の余韻”を上品に伝えよう
「残炎の候」は、夏の終わりの“残る暑さ”をやわらかく表す言葉です。
この表現は、真夏のような激しい暑さではなく、少しずつ落ち着き始めた日差しや夕暮れの風に感じる穏やかな熱気を表しています。
「夏の余韻を楽しみながら、秋の訪れを待つ」という気持ちをやさしく伝えることができるのが魅力です。
時期や相手に合わせて上手に使うことで、相手に季節の移ろいを感じてもらえるだけでなく、あなたの心配りや礼儀正しさも自然に伝わります。
また、手紙やメールの中にこの一言を添えることで、文章全体に上品さと温もりが加わり、読む人の心をふっと和ませる効果もあります。
ほんの少しの工夫と心配りで、あなたの手紙やメールがぐっと品よく、やさしい印象になりますよ🌿
季節を感じる言葉を意識的に取り入れることで、何気ない文章にも深みと情緒が生まれ、相手との距離をあたたかく縮めることができるでしょう。